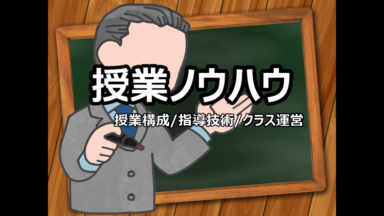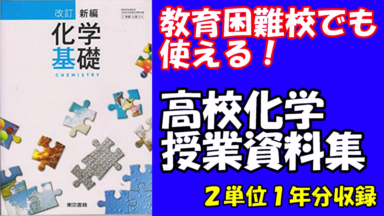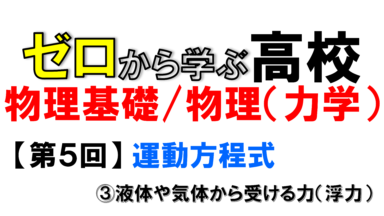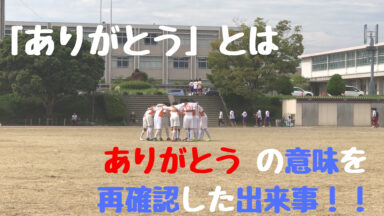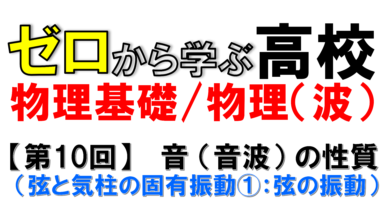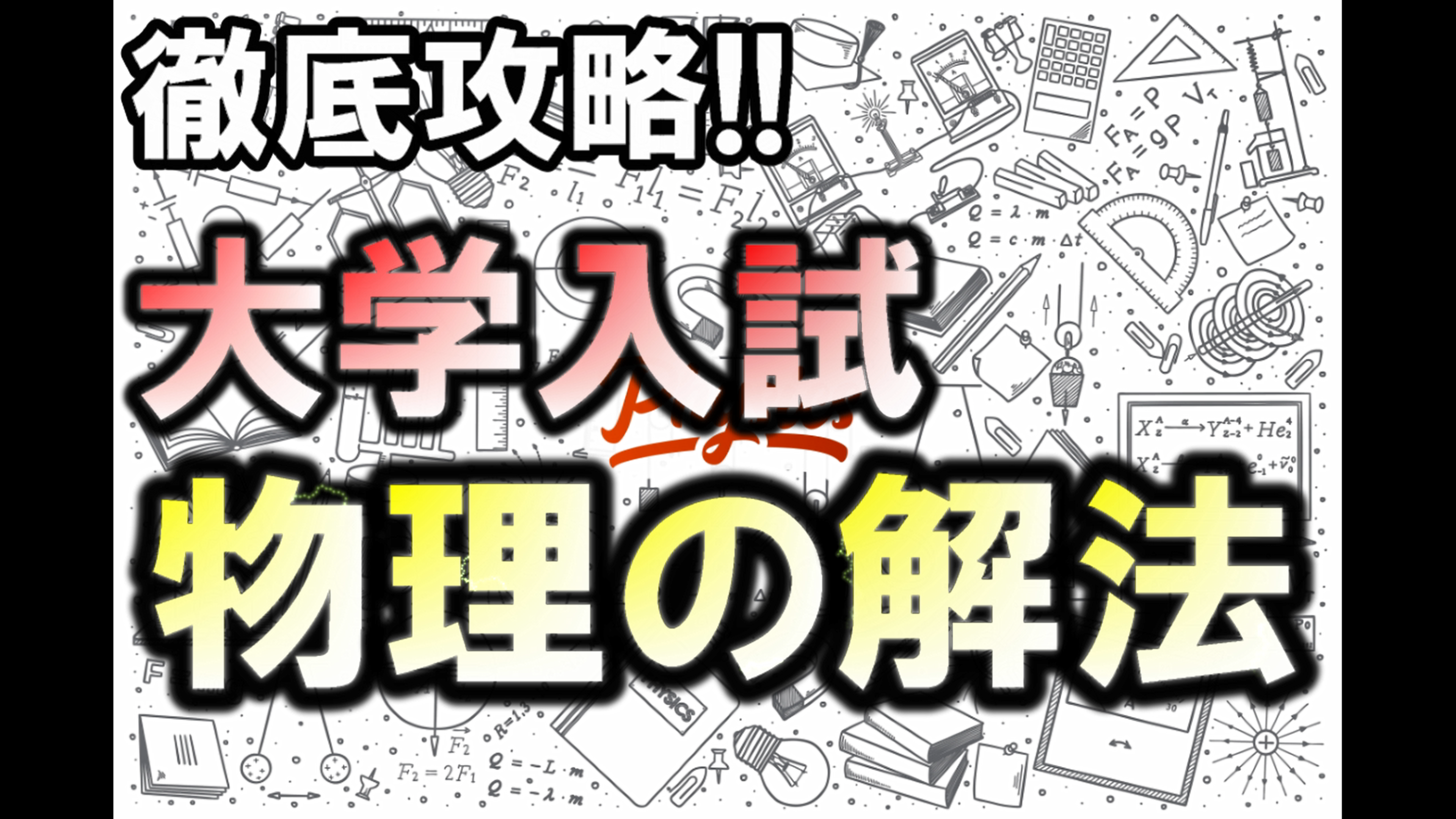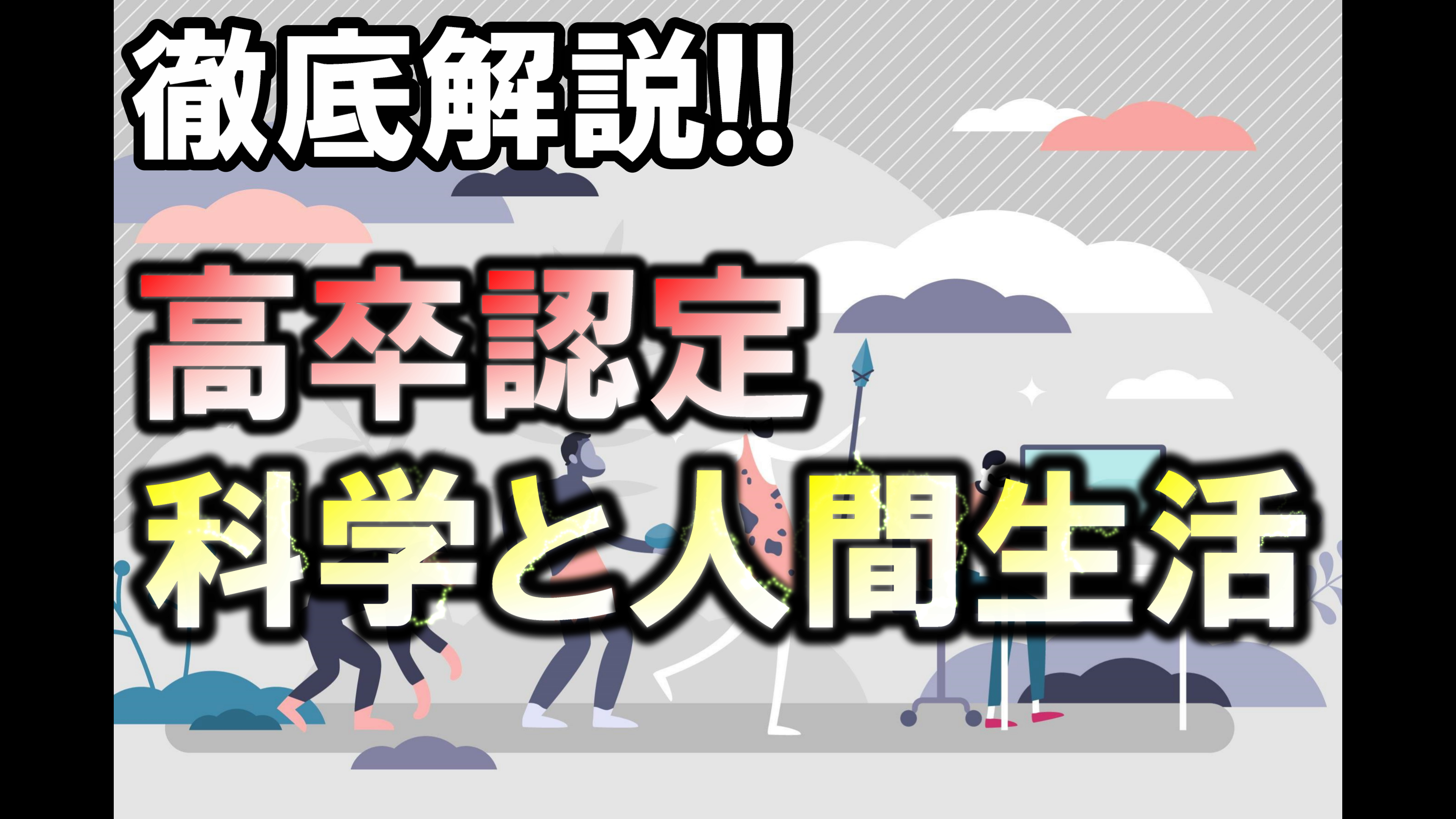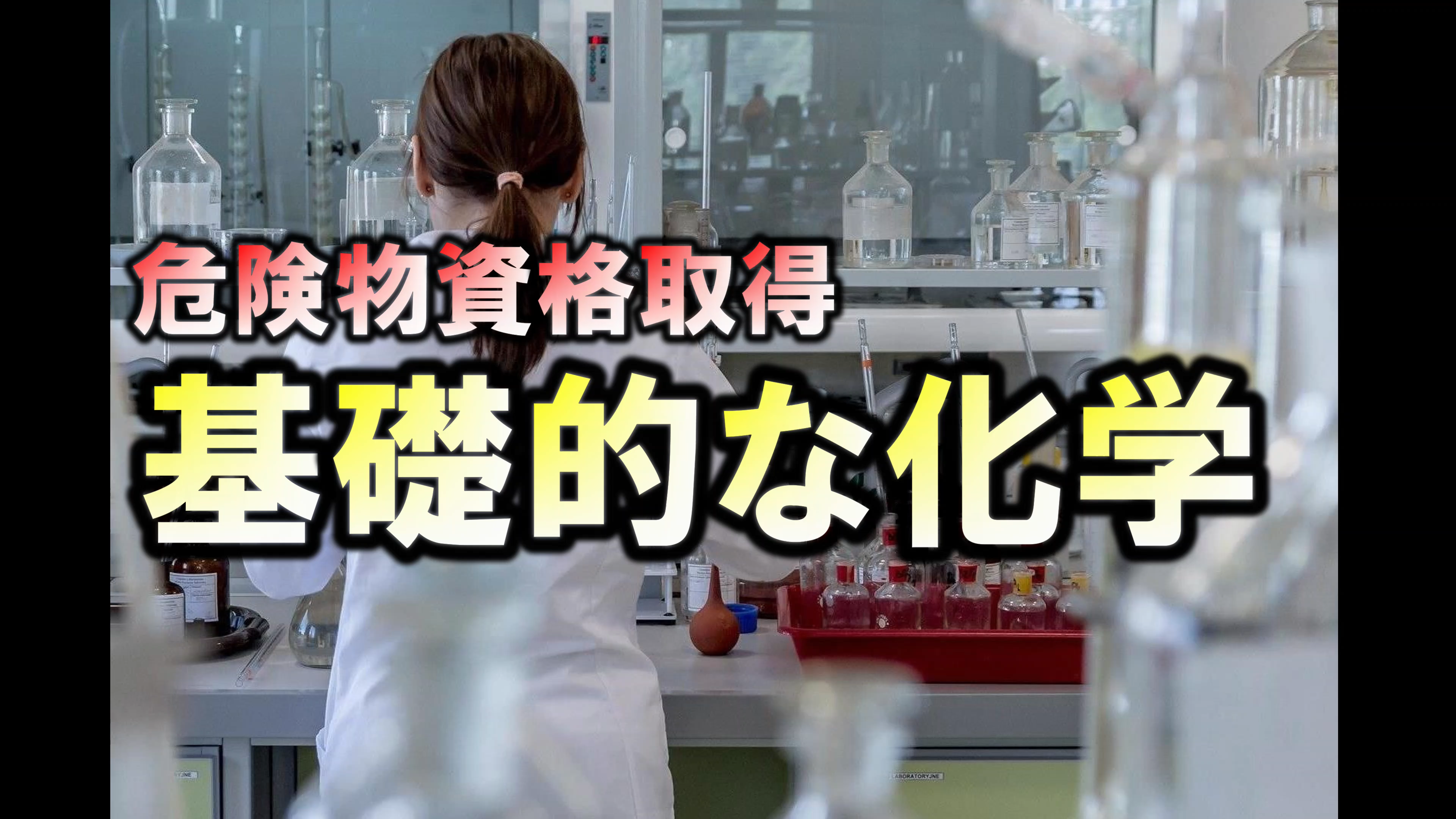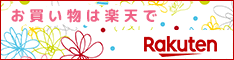実験室で授業を行うのは難しい。
教室で行う授業とは異なった注意点が多数存在する。授業の基本シリーズ No.2において、教室における授業の組み立て方に関する記事をお届けしたが、学習意欲が低い生徒たちにとっては、どれだけ配慮しても教室での授業が続くと退屈してしまう。
特に理科の授業だと小学生、中学生の時に実験や工作の授業を経験してきたこともあり、そのような授業に対する期待感がそれなりにある。座学の授業が続いてしまうと、生徒たちの期待を裏切る結果となってしまい、学習のモチベーション低下につながっていく。

■教室配置の問題点について


1つ目に、室内空間が広く、黒板前にある教卓が教室のものと比べて大きい。2つ目に、椅子に背もたれがついていない。3つ目に、机がつながっている。(4人掛け用のテーブルになっている。)
これらの違いによって、引き起こされる問題として、まず室内空間が広いことにより、生徒との距離感が非常に遠くなる。そして、黒板の前で説明を行っている際に、騒がしい生徒を直接注意しようと机間巡視を行おうとしても、前に広がる教卓が常に教師を妨害して、うまく指示や注意が届かないのである。
授業者の指示を生徒がきちんと聴いて、適切に行動してくれるのであれば、この手の心配は無用であるが、残念なことに、実験室のレイアウトは生徒が騒がしくなり易くなるトラップが潜んでいる。
そのトラップに相当するものが2つ目と3つ目の違いに関係する。

後ろを向いてしゃべっていたら、注意するのは当然であるが、更に残念なことに教室の机とは異なり、テーブルが4人掛けになっており、隣の生徒との心理的な境界が取り払われて、隣同士でも私語をしやすい状況なのである。生徒たちの興味・関心を引くために手暇をかけて準備した実験授業だけど、いざ授業が始まると、本題に入る前にざわざわ。
何度か注意を繰り返すも、私語が鳴りやまない、堪忍袋の緒が切れて、とうとう大声を出してしまい、ようやく静まり返るも、終始お通夜のような授業。
これなら、教室で普通に授業やっておけばよかった!
と後悔の念。
他教科と差別化を図ろうと斬新な授業に挑戦するにしても生徒たち集団の行動原理を理解していないと、ことごとく失敗してしまう。
次回の実験室での授業シリーズでは、この問題も含めた、実験授業を準備・実行していくための技術についてお伝えしていく予定である。
授業の技術シリーズ(続き)はこちらのガイドを活用ください。
授業資料集